17年・1500名の支援から見えた「子どもが変わる家庭の共通点」
今回は、私が心理カウンセラーとして17年間、1500名以上の親子と接してきた中で感じた、
「子どもが変わる家庭に共通するパターン」についてお話ししたいと思います。
現代の家庭に見られる傾向
現代の社会は、少子化の影響もあり、子どもの教育や生活に対してより熱心な親御さんが増えています。
一方で、フルタイムやパートタイムで働くお母さんも多く、仕事・子育て・家事の負担からストレスを抱えている方も少なくありません。
本当に皆さん、日々よく頑張っていらっしゃると感じています。
「親が変わる」家庭の共通点
子どもが変わる家庭に共通しているのは、お母さんが中心となり、子どもと向き合い続けているということです。
特に、「傾聴・共感」がしっかりできるようになったお母さんの家庭では、子どもが大きく変化します。
カウンセリングに来られた当初から、傾聴・共感ができているお母さんは、ほとんどいません。
しかし、回を重ねるうちに少しずつスキルアップし、ご自身と子どもの気質を理解し、
話を聴けない原因(怒り、不安、心配からの根掘り質問、無自覚なアドバイスなど)を整理していくと、
驚くほど傾聴・共感ができるようになっていきます。
その結果、子どもに次のような変化が見られるようになります。
- 甘えてくるようになった
- 笑顔が増えた
- 会話を避けていたのに、自分から話しかけてくるようになった
- 外に出るようになった
このような変化が継続していくと、さらに大きな成長へとつながっていきます。
自己流では限界がある理由
自己流でも「傾聴・共感」を意識して取り組むだけで、一定の変化は見られることがあります。
しかし多くの場合、無自覚のアドバイス・提案・意見の挿入があるため、そこで止まってしまうのです。
本当に大切なのは、共感の前に意見を言わないこと。
そして、質問の仕方・伝え方・ほめ方なども、子どもの自立心を育てる大切な要素です。
家庭全体に広がる好影響
お母さんの変化は、子どもだけでなく兄弟姉妹にも良い影響を与えます。
問題を抱えていない兄弟が勉強や運動に意欲的になったり、
友人関係が改善されたりするケースも多く見られます。
また、問題を抱えていた子どもも、「親が自分を理解してくれる」という安心感の中で少しずつ心を開き、
自分の気持ちを話せるようになり、明るくなり、自立心が育っていきます。
心理カウンセリングが必要なタイミング
もし子どもが「変わりたい」と思っていても行動できない場合、
多くは心の傷が影響しています。
その場合は心理カウンセリングを受けることが望ましいです。
自分の傷を自分で癒すのは難しく、克服までに長い時間がかかることが多いからです。
お父さんの役割と家庭のサポート
家庭では、お父さんが「お母さんのサポート役」として関わることが理想です。
お母さんの気持ちや愚痴を聴いてあげるだけでも十分な支えになります。
ただ、実際にはワンオペ育児の家庭も少なくありません。
それでも、お母さんの努力によって子どもが変化していった家庭を、私は数えきれないほど見てきました。
うまくいかない家庭に共通する傾向
うまくいかない家庭では、多くの場合、お母さんが忙しすぎてストレスフルになっていることが共通しています。
会話が減り、良い接し方を意識できなくなり、時には諦めの気持ちが生まれてしまうのです。
しかし、「続けること」こそが最大の力です。
少しずつでも継続していけば、状況が変わる家庭は本当に多いのです。
17年間の支援を通して感じること
これまで多くの家庭と関わらせていただき、私自身もたくさんの学びを得てきました。
子どもが成長し、初めて会った頃と別人のように変わっていく姿を見ると、
胸が熱くなり、時には涙が出そうになることもあります。
そして、お母さん自身が変化し、家庭が好循環になっていく姿を見たとき、
「この仕事をしてきて本当によかった」と心から感じます。
私はこれからも、歩みを止めるつもりはありません。
それが、私の使命だと感じているからです。
おわりに
子どもが変わる家庭には、必ず「親の変化」があります。
傾聴・共感・理解を積み重ねていく中で、家庭全体が変わっていきます。
その変化の連鎖が、子どもの未来を明るく照らしていくのです。
今日も少しだけ、やさしい気持ちでお子さんと向き合ってみてください🌿
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。


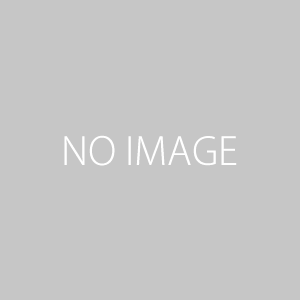
この記事へのコメントはありません。