やる気が出ないのは怠けではない。子どもが動けない本当の理由
「やればできるのに、なぜか動けない」
「何度言っても同じことの繰り返し」
- 勉強しない
- 学校に行かない
- 話しかけても無反応
- ゲーム・スマホばかり
そんな子どもの姿に、戸惑う親御さんも多いのではないでしょうか。
実は子どもは、“動かない”のではなく、“動けない”状態のことがほとんどです。
子どもが動けなくなる背景
子どもが動けなくなる原因は、次のような心理的要素が絡み合っています。
- 心の傷による無意識のブレーキ
- 失敗が怖い
- 人の目が気になる
- 「どうせやってもダメ」と思ってしまう
本人は無自覚なことが多く、“やる気”や“努力不足”の問題ではありません。
心の奥にある「過去の傷」や「気質」「環境」などが影響しているのです。
環境・気質・心の傷の関係
● 環境の影響
学校や家庭などでのストレスが積み重なることで、心は萎縮していきます。
たとえば、いじめ・人間関係・苦手教科・先生との相性など、本人が頑張っても避けられない環境が続くと、心が「もう無理」と反応します。
● 気質の影響
心配性の「不安気質」や、完璧を求める「執着気質」をもつ子どもは、小さな失敗にも過敏に反応してしまいます。
「悪い方向に考える」「細かいことが気になってイヤになる」など、自分で自分を縛る傾向が強くなるのです。
● 心の傷の影響
こうした環境や気質が重なると、“心の傷”が潜在意識の中に封印されてしまいます。
「自分の意見を否定された」
「頑張っても認められなかった」
「親や友達に合わせすぎて疲れた」
このような体験が積み重なると、「もう傷つきたくない」という無意識のブレーキがかかり、行動が止まってしまうのです。
親の「良かれと思って」が逆効果になることも
子どもが動かないと、つい口を出してしまう。
そんな親御さんも多いのではないでしょうか。
- 先回りしてやってしまう
- 命令・指示・アドバイスを繰り返す
「早く寝なさい!」「もう宿題やったの?」「時間でしょ、急ぎなさい!」
これらは子どもの左脳に作用し、「うるさいな」「わかってるよ!」という反発を生みやすくします。
たとえ言うことを聞いたとしても、“自分の意思で動いた”わけではないため、自立心が育たず、依存的な行動パターンが強まってしまいます。
解決の鍵は「寄り添い・傾聴・共感」
一番大切なのは、子どもの心に寄り添うことです。
- 否定せずに話を聴く
- 共感する
- すぐにアドバイスをしない
たとえ興味のない話でも、「そうなんだね」と受け止めるだけで十分です。
子どもは「わかってもらえた」と感じることで安心し、自分の中から「こうしたい」という意欲が生まれます。
自分で気づいたことは、自分で行動できます。
この“自発的な気づき”こそが、子どもを変えていく力です。
親が変われば、子どもは変わる
多くのお母さんが「傾聴しているつもり」でも、実際にはつい助言したり、先回りしたりしてしまいます。
それは親御さん自身の「心配」「不安」「焦り」が原因のこともあります。
だからこそ、親の心を整えることが、子どもが変わる第一歩。
親の心理カウンセリングによって、心配や不安を手放せると、子どもへの関わり方が自然と変わります。
おわりに
子どもが“動かない”のではなく、“動けない”状態にあると知ること。
それが、親子関係を変える最初の一歩です。
子どもが家庭で安心して話せる環境があれば、やがて自分で気づき、自分で動けるようになります。
今日も少しだけ、やさしい気持ちで子どもの声を聴いてみてくださいね🌿
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。


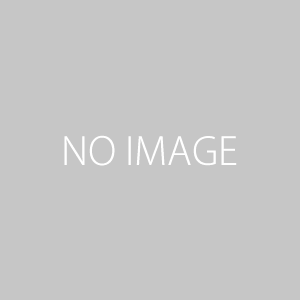

この記事へのコメントはありません。